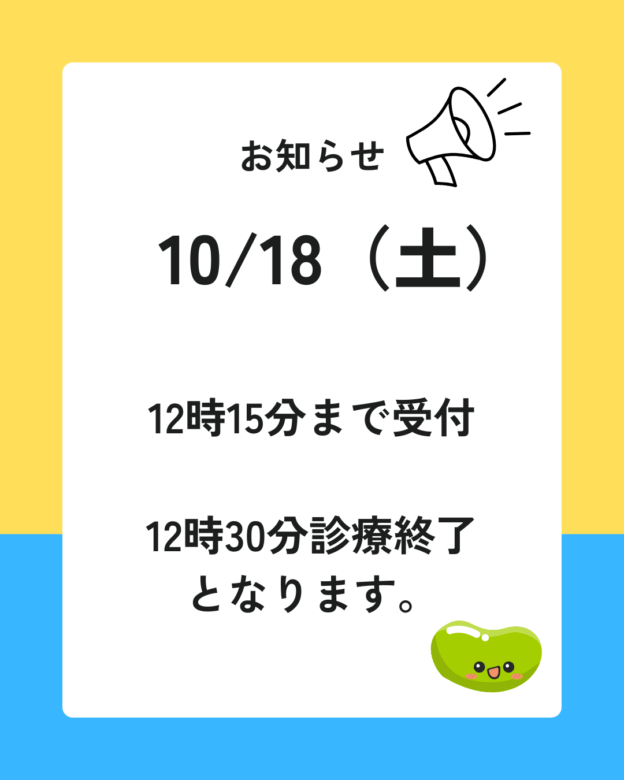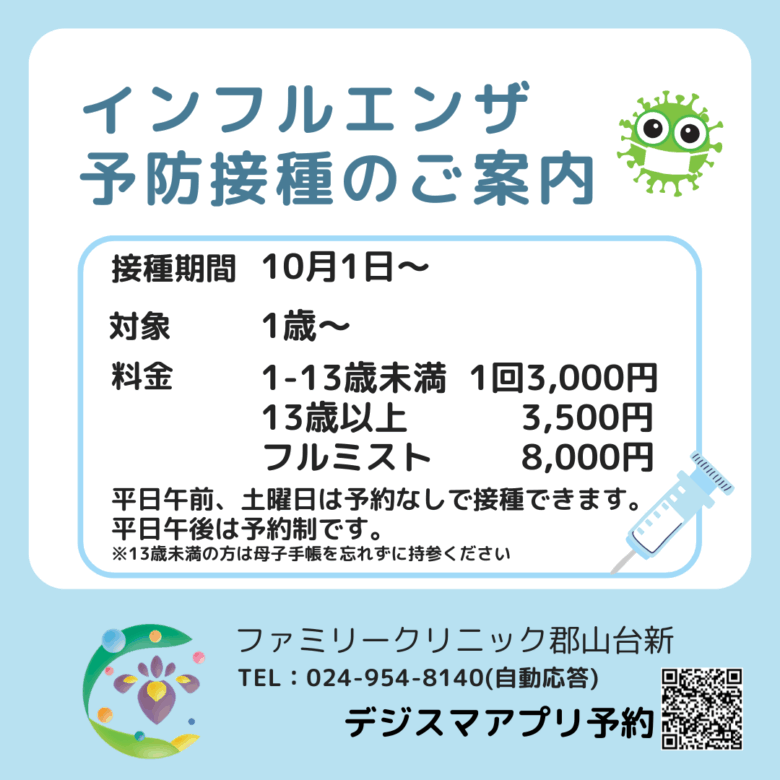
保健医療機関における掲示事項
在宅医療情報連携加算及び在宅歯科医療情報連携加算について
当院ではICTツール【医療介護専用のコミュニケーションシステム 「メディカルケアステーション」(MCS)】を使用して、 事業所間で情報共有を行っております。
- 主な連携機関●
訪問看護ステーション・エフズ
アイリス訪問看護ステーション
訪問看護ステーション亀田
星訪問看護ステーション
医療DX推進体制整備加算について
① 医師等が診療を実施する診察室等において、 オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を 活用して診療を実施しています。
② マイナ保険証を促進する等、医療DXを通じて 質の高い医療を提供できるよう取り組んでいます。
一般名処方加算について
昨今、医療用医薬品の供給状況が不安定なことから、 当院では処方箋の交付にあたり、一般的名称(※) にて薬剤を記載しています。 また、⾧期収載品について、医療上の必要性が 認められない場合で、患者様が⾧期収載品を希望する場合は 選定療養となります。 一般的名称にて処方することで、調剤薬局において 同一成分・剤形・含量の薬剤を選択することができ、 不安定な供給状況緩和の一助となり得ます。 一般名処方にご理解頂き、ご不明な点は医師又は職員までご相談下さい。
※一般的名称=「成分名+剤形+含量」で表記したもの。
「医療情報取得加算」について
当院では、初診料・再診料に「医療情報取得加算」を加算しています。 この加算は「オンライン資格確認を導入している保険医療機関に おいて、初診時や再診時に患者の薬剤情報や特定健診情報等の診療 情報を活用して質の高い診療を実施する体制を評価するもの」とし て位置づけられており、当院では以下の体制を有しています。 ① オンライン資格確認を行う。 ② 当院を受診した患者様に対し受診歴、薬剤情報、特定健診情報 その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行う。 なお、マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局は以下で検索できます。
厚労省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html
外来感染対策向上加算に関する掲示事項
- 院内感染対策に係る基本的な考え方 院内感染の防止に留意し、感染等発生の際にはその原因の速やかな特定、制圧、終息を図ることは、 医療提供施設にとって重要である。院内感染防止対策を全従業員が把握し、指針に則った医療が 提供できるよう取り組む。 (2)院内感染対策に係る組織体系、業務内容 感染防止対策部門を設置し、院内感染管理者(管理者)を配置した上で、感染防止に係る日常業務を行う。 (3)院内感染管理者の業務内容 ① 1週間に1回、院内を巡回し、院内感染事例の把握を行うとともに、院内感染防止対策の 実施状況の把握・指導を行う。 ② 院内感染対策指針及びマニュアルの作成・見直しを行うとともに全職員へ周知する。 ③ 院内感染対策に関する資料を収集し、職員へ周知する。 ④ 職員研修を企画・実施する。 ⑤ 院内感染が発生した場合は、速やかに発生の原因を究明し、改善策を立案し、 実施するために全職員への周知徹底を図る。 ⑥ 総合南東北病院(A234-2 感染対策向上加算1の届出病院)が定期的に主催する 院内感染対策に関するカンファレンスに年2回以上参加する。 ⑦ 総合南東北病院が主催する新興感染症の発生等を想定した訓練に年1回以上参加する。 (4)感染性疾患への対応 感染性の高い疾患が疑われると医師が判断した患者様は、一般診療の患者様と動線 又は時間を分けた診療を行う。 (5)抗菌薬適正使用のための方策 最新のガイドラインに則り、医師の診察の結果抗菌薬の使用が必要であると判断した場合のみ、 必要十分な量を処方する。 (6)他の医療機関等との連携体制 総合南東北病院と連携し、院内感染に関するカンファレンスへの参加、新興感染症の発生等を想定した 訓練への参加、院内の抗菌薬の適正使用に関する助言を受ける等を行う。
時間外対応加算3の算定について
当院を継続的に受診している患者様からの電話等 による問い合わせに対し、標榜時間外の夜間の数時間(22 時まで)は、 原則として当院において、 当院の常勤の医師、看護職員又は事務職員等により、 対応できる体制を有しています。
緊急連絡先:024-954-8140
標榜時間内や標榜時間外の夜間の数時間(22 時まで)に、 やむを得ない事由により、電話等による問い合わせに 応じることができなかった場合であっても、 速やかに患者様にコールバックします。 ※)時間外対応加算3は再診料を算定する全ての患者さんに算定します。
⾧期処方・リフィル処方せんについて
当院からのお知らせ 当院では患者さんの状態に応じ、 ・ 28 日以上の⾧期の処方を行うこと ・ リフィル処方せんを発行すること(※) のいずれの対応も可能です ※なお、⾧期処方やリフィル処方せんの交付が対応可能かは 病状に応じて担当医が判断致します
ファミリークリニック郡山台新の公式サイトがオープンいたしました
ファミリークリニック郡山台新のホームページにアクセスいただき、誠にありがとうございます。
この度、ホームページを新規に作成いたしました。
ご満足いただけるホームページを目指して、コンテンツの拡充等を行う予定ですので、今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。